日本臨床発達心理士会第21回全国大会
「社会的コミュニケーション発達を促す親子遊び」実践研究発表 シンポジウム②S2
日 時:2025年8月24日(日)15:00~16:30
参加者:53名
【企画者】テーマ別研究会「ふれあいプログラム研究会」
【話題提供者】尾崎康子、石山玲子、東都ガーボル、三宅篤子
【司会者】尾崎康子
*ゲストスピーカー:西尾大輔(厚生労働省 社会・援護局障害福祉部 障害福祉課地域生活・発達障碍者支援室 発達障害対策専門官 臨床発達心理士)

社会的コミュニケーション発達が困難な発達障害児、特にASD児に対して社会的コミュニケーション発達を促すふれあい遊びについてその理論と実践の活動事例を紹介するシンポジウムを開催しました。「社会的コミュニケーション発達を促す親支援と親子遊び」の情報交換会に引き続き参加された方もおり、シンポジウムには多くの参加がありました。参加者には「社会的コミュニケーション発達を促す親子遊び」に興味や関心を持ってもらい、乳幼児期に「遊び」を通して社会性を獲得していくことの重要性と効果一緒に考える場を設けることができました。
最初に尾崎先生より親子ふれあい遊びの背景理論と留意点について説明があり、社会的コミュニケーション発達に遅れがある子どもが、親子ふれあい遊びを通して親子の関わりを持つことの重要性が話されました。
次に、石山先生からは「ふれあいペアレントプログラム」に参加した2~5歳児の家族(3ケース)の実践報告がありました。実施後のアンケートの振り返りから「ふれあいペアレントプログラム」の良さと課題、また参加者同士のエンパワメントについて報告されました。
東都先生からは発達年齢別の遊びと効果に関する発表があり、人間には内部からうける刺激と外部から受ける刺激の7感があることなどスライドと実際の遊びを通して紹介がありました。

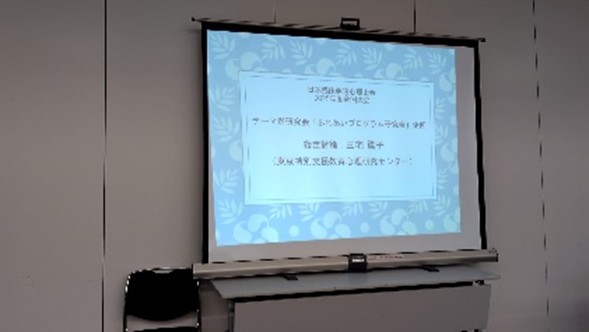
三宅先生の指定討論では、親子ふれあい遊びの長所、行う際に配慮したこと、考え方に合わせて大切なことについて質問がありました。3名の話題提供者から様々な視点にたった意見を聞くことができました。最後に、西尾先生から「切れ目のない支援」を家族と一緒に応援していきたいとコメントをいただきました。
今回のシンポジウムの討論を通して、参加者が親子遊びの重要性を共有し、「実際にやってみたい!」という熱意の共有をもてたと思いました。
(報告:和田美奈子)
日本臨床発達心理士会第21回全国大会 テーマ別研究会「ふれあいプログラム研究会」主催
「社会的コミュニケーション発達を促す親支援と親子遊び」情報交換会を開催しました。
詳細はこちらからご覧ください。
日本臨床発達心理士会全国研修会 公開講座 テーマ別研究会「ふれあいプログラム研究会」主催
「親子ふれあい遊びワークショップ~発達が気になる子と親の支援者が学ぶ遊びの理論と実践~」
日時:2025年8月9日(土)13:30~16:40
参加者:臨床発達心理士正会員 30名 非会員11名 合計41名
【講師】尾崎康子(東京経営短期大学)東都ガーボル(相模女子大学)
藤川志つ子(敬愛短期大学)和田美奈子(認定こども園相模女子大学幼稚部)

昨年の全国大会で開催したワークショップについて、今回は会員以外の発達支援関係者にも広く告知し、ふれあいプログラム研究会主催の全国研修会として実施しました。参加された方の殆どの方が、親子支援の現場に携わっていることもあり、会場となった相模女子大ガーデンホールは、開始直後から外の気温に負けないくらいに先生方の熱気にあふれていました。講座の冒頭で講師から「子どもと遊ぶことが苦手な親がいることを忘れない」「親ができる親子遊び」がキーポイントと伝えられると、深く頷く参加者が多く確認されました。子ども支援を生業とする参加者は忘れてはならない視点の一つと思います。
講座は、本講座の軸となる「親子ふれあい遊び」の基礎理論である発達論的アプローチを学んだ後に、参加者が疑似的な親子になり身近な道具を使って①人とのやりとりを育む親子ふれあい遊び②グループで行う親子遊び③感覚や運動を育てる親子ふれあい遊びを40分間ずつ、しっかり体験するという構成で実施いたしました。親子ふれあい遊びは「人との相互的関わり」「共同注意」「感情と気持ちの共有」を獲得することに適した遊びではありますが、講師から遊びを行う前提として、子どもの身体機能や五感や二覚の発達や個人差を意識することの大切さに話が及ぶと、「あー」と言った気づきの声が会場のあちこちから聞かれました。また、一つに遊びのなかに様々な発達を促すエッセンスが入っていること、遊びを進める上では、少し先の発達を見据えながら関わりをもつことの大切さの再確認できたのではないでしょうか。



親子ふれあい遊びの『ふ・れ・あ・い方略』を意識しながら、子どもの発達段階を踏まえ親子の関わりを提案することや、やりとりを楽しみながら遊び充実させるヒントを互いにもらえた時間になったと思います。 (報告 藤川志つ子)
